 |
 |
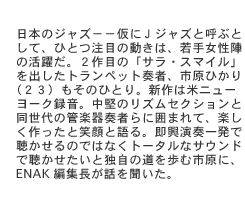 |
|
 |
|
 ジャズの世界で女性演奏家が台頭するのは、学校の吹奏楽部に占める女子生徒の割合が圧倒的になっていることと無縁ではないだろう。市原も中学高校と吹奏楽部に在籍した。
ジャズの世界で女性演奏家が台頭するのは、学校の吹奏楽部に占める女子生徒の割合が圧倒的になっていることと無縁ではないだろう。市原も中学高校と吹奏楽部に在籍した。
 ただ、女性が増えたといってもトランペット奏者はまだ少ないかもしれない。トランペットという楽器は、本当はそんなことはないのだけど−−素人目には唇を酷使しそうだし、ほおをいっぱいにふくらませて吹く人もいたりして、そのビジュアルはなんとなく女性向きではないのかもしれない。
ただ、女性が増えたといってもトランペット奏者はまだ少ないかもしれない。トランペットという楽器は、本当はそんなことはないのだけど−−素人目には唇を酷使しそうだし、ほおをいっぱいにふくらませて吹く人もいたりして、そのビジュアルはなんとなく女性向きではないのかもしれない。
市原はなぜトランペットを選んだのか?
「小学3、4年生のときに演奏を見た“トランペットのおにいさん”が、俳優の玉木宏さんに似てかっこうよかくって、それでトランペットってかっこいいなあと」
父親はジャズピアニストの鈴木宏昌氏のバンドやスタジオミュージシャンとして活躍するドラム奏者、市原康。だから、幼少のころから音楽に囲まれていたが、さすがに音楽家の父親は持論をもっていて「指導者との相性で嫌いになるおそれもある」とピアノを習わせたりはしなかった。したがってトランペットについては市原が自発的に興味をもったというわけだ。その端緒がイケメンだったというのはいかにも女の子らしいか。
ともかくその印象が強烈だったから、中学で吹奏楽部に入りトランペットを選んだ。さらに中学3年生でトランペット奏者、エリック・ミヤシロの演奏を聴いて本格的にのめり込むことになる。
ハワイ出身のエリックはスタジオミュージシャンとしてSMAPやMISIAらJポップのきらびやかな人気者たちの作品の録音に参加。一方、ミュージシャン仲間を集めたEM BANDを結成し、ライブ活動などを続けている。
市原が衝撃を受けたのもEM BANDのライブだった。
「ひどくカッコよかったんですよ。カッコよくてカッコよくて。ライブのたびに制服姿で東京・新大久保のライブハウスとかに通い詰めました。父親に勧められて見にいったんですけど」
これがジャズなのかという衝撃もあった。
「あの方たちの中で自分も吹きたい。じゃあ、ジャズを勉強しなくちゃ」
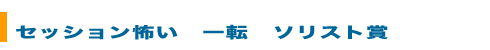 洗足学園音楽大学のジャズコースに進んだ。
洗足学園音楽大学のジャズコースに進んだ。
受験時、ジャズについてはよく分からなかったので、試験科目の即興演奏のあきらめたが、他の科目だけは完璧にこなしたと振り返る。
 そんな市原にとってジャズの勉強の日々は驚異でもあり、新鮮でもあった。学生同士のジャムセッションには怖くて3年生になるまでは加われなかった。高校時代から即興演奏を学んでいる強者もざらだったのだ。
そんな市原にとってジャズの勉強の日々は驚異でもあり、新鮮でもあった。学生同士のジャムセッションには怖くて3年生になるまでは加われなかった。高校時代から即興演奏を学んでいる強者もざらだったのだ。
「落ちこぼれだったんですよ」
しかし、講師を務めたトランペット奏者、原朋直の巧みな指導によりめきめきジャズを理解した。
「エリック・ミヤシロさんに出会ってジャズに進む気持ちが固まり、原さんに出会って即興演奏を追究しようと決意した。このふたりが私の人生の道しるべです」
セッションが怖かったのが一転、積極的に加わるようになり、ついに敬愛するEM BANDのライブに参加する機会を得た。
「いつの間にか図々しくなってしまいました。でも、努力もしたから。独奏も与えられたおかげで人生最大の緊張を経験しました。ほかのことでこれ以上緊張することはないだろうと考えたら、それ以後はあまり緊張しなくなりました。ステージ上での自分を客観視できるようにもなりました」
さらに4年生のときには早大の老舗学生ビッグバンド、ハイ・ソサエティ・オーケストラにも客演として加わり、学生ビッグバンド大会に参加。優秀ソリスト賞を獲得した。
評判が広がったのか、在学中にCDデビューの話が舞い込んだ。
「とてもありがたいお話でした。EM BANDで演奏したいという目標がかない、次は漠然とCDを出したいなと思っていたんです」
 05年3月に大学を卒業。同年8月に初作「一番の幸せ」を出した。
05年3月に大学を卒業。同年8月に初作「一番の幸せ」を出した。
 「一番の幸せ」はユニークな作品だった。日本語ロックの草分け、はっぴいえんどなどで活躍したギター奏者、鈴木茂を迎えて自作曲で固めた。
「一番の幸せ」はユニークな作品だった。日本語ロックの草分け、はっぴいえんどなどで活躍したギター奏者、鈴木茂を迎えて自作曲で固めた。
賛否両論だった。作品の内容以前にイメージ戦略のうえで、だ。ジャンルを超えた意欲作は、しかし名刺代わりの作品としては市原の立ち位置が見えづらかった。
「自分の中のいちばんベーシックな音楽−−1970、80年代の米国のポップスとかAORを基本に据えたのですが、それがいけなかったのかなあ。おもしろかったんですけど、理解されなかったり、自分の力不足もありました。ある方がおっしゃるには新人がやるにはジャンルの“浮遊感”がありすぎて分かりづらい。確かにそうかもしれません。でも、やれることはやったので、これからもっとがんばって、多くの方に私のことを認めていただけた際にもういちど聴いていただいたら、評価は変わると考えています」
いずれにしろ消化不良だった。そして次の目標を立てた。海外録音。EM BANDと演奏したい。CDを出したい。目標は次々にかなったが、今回もそうなった。特別にリクエストしたわけではないのに。
「1作目を出した後、考える時間がたくさんありました。演奏する機会より考える時間のほうが多かったぐらい。考えに考えていろんな方と話し合って、いま自分がいるべきなのはどこなのか。やるべきことはなんなのかと考えた結果がこれです」
「サラ・スマイル」。ニューヨークでスタンダードソングや既存の有名曲を素材にしたストレートなジャズを録音した。
「オリジナルの楽曲を聴いていただくためには、まずは大勢の方が知っている、親しみのある曲を聴いていただくのがよい。知っている曲を聴く安心感って大きなものでしょうし、それがほかの曲を聴くときの心の持ちように影響してくると考えました」
 こんな感じのドラム奏者がいい−−など、漠然としたリクエストに対してニューヨークのコーディネーターが演奏家を集めた。
こんな感じのドラム奏者がいい−−など、漠然としたリクエストに対してニューヨークのコーディネーターが演奏家を集めた。
その結果、ドラムとベースはもはやベテランといっていいルイス・ナッシュとピーター・ワシントンが選ばれた。テナーサックスのグラント・スチューワートはひとまわり上の35歳。ピアノは3歳上の新鋭アダム・バーンバウム。そしてもうひとりのトランペット奏者、ドミニク・ファリナッチはひとつ下。
「ほぼ同い年のドミニクついては、ライバル視して普通はがんばらなくちゃ、くやしいという気持ちが起こるのでしょうけど、とにかく演奏がうまくて。会話をしてみたら、彼がうまいにはそれだけの理由がある。はんぱじゃない努力。研究。そのうえ人柄もよくて、それを知ったら尊敬しながら演奏できました。だからよかった。ワクワクしながら吹けたので、自然な形で録音できました」
アルバムの表題曲で80年代米ポップグループ、ホール&オーツの「サラ・スマイル」は市原のお気に入り。だから客観視するため、あえて編曲はドミニクに頼んだ。
その出来には「びっくりした。『あんた天才だね』ってほめたら最初のうちは謙遜していたのに、次第に『そうだろ?』っていばり始めて! すごくよい友人をみつけました。同じトランペット奏者でこんなによい友人ができるとは思ってもいませんでした」
 ルイスとピーターのベテラン勢は比較的淡々と仕事をこなしたというが、それでもチームワークはよかった。
ルイスとピーターのベテラン勢は比較的淡々と仕事をこなしたというが、それでもチームワークはよかった。
「ルイスはドラミングで道しるべを作ってくれるんですよ。私がもうあと少し吹くべきか否か迷いの起きない演奏。つまり、ルイスがまず方向を決めて、ピーターが歩きやすく固めて、そうしてできた“道”にアダムが花を咲かせたり木を植えたり、きれいな風景にする。そこを私が歩く。みんなが土台を作ってくれるので、私はなんの苦もなく歩けました」
ぐっと、いわゆるジャズらしさを表に出したが、自分の目指す方向は変わりない。
「1作目も音色は自分の音色。どちらも楽曲を聴いてもらいたい。アドリブじゃなくて、まずは楽曲を。その点は一貫しています。ライブでもそう。トータルで作品として聴いてもらいたいんです。気に入っていただいたらどう楽しむかは聴き手におまかせしますけれど、私としてはまず楽曲をと考えています。ライブでもめったなことがない限りアドリブ中心にお聴かせすることはありません」
アーティストとして自分の方向というものをしっかりともっている。同時に演奏家としては常に向上を目指したい。できれば留学して2年ぐらい演奏の勉強に没頭したいという。
トランペットは女性向きじゃない、とは考えていない。
「トランペットを吹くのに体格は関係ありません。肺の大きさは多少あるでしょうけど、効率よく吹けば男女は関係ないと思います。そのことが広く認知されていないのではないでしょうか。教育の現場でもわりと“根性一発”みたいな教え方が多いみたいですし。まあ、吹いている姿があまりカワイクない。かわいい顔もできないという側面はありますけれど。あと絶対的なアイドルが登場していませんね。女性サックス奏者で人気を博したキャンディー・ダルファーみたいな人が」
それはあなたがなるのではないかと水を向けると、「なれたらいいなぁ〜」と、なんだか天真らんまんに笑った。
産経Webは、産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。
すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)
(C)2006.The Sankei Shimbun All rights reserved.
Sara Smile ポニーキャニオン PCCY60003 ¥3,000 PROFILE いちはら・ひかり 1982年12月22日生まれ 成蹊小学校、中学校、高等学校を卒業 中学入学と同時にトランペットをはじめ、高校1年よりトランペット奏法を池田英三子氏に師事 洗足学園音楽大学ジャズコースに入学し、4年間ジャズ奏法を原朋直氏に師事 2004年山野ビッグバンドコンテストでソリスト賞受賞 2005年3月洗足学園大学卒業、優秀賞受賞 在学中より同年代メンバーで構成されたバンド、hip chickで都内にて活動 ●公式サイトはこちら |

