 |
 |
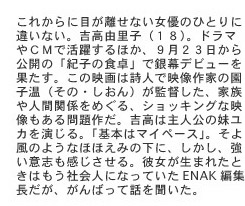 |
|
 |
|

島原紀子(吹石一恵)は17歳の平凡な女子高生。地方の町で暮らす紀子は、多感ゆえに親子関係にいらだちを感じて家出し、東京でレンタル家族の一員になる。姉を探して上京した妹のユカ(吉高)もまた、レンタル家族に加わる。娘たちの行方を突き止めた父親の徹三(光石研)は、娘たちを指名して家族をレンタルする。再会した親娘は…
こう書くとこの映画、親子の絆を再確認する、風変わりながらもほのぼのとした作品のようにも見えるが、とんでもない。時に奇妙で時にドギツイ映像を用いて園監督は観客にさまざまに問いかけてくる。
もうオジサンのENAK編集長の心に残ったのは、漠然とした疑問や不安だけ。もっと若く、しなやかであれば違うことを感じたのだろうか。だが、この映画はそれでいいのかもしれない。観る人が、それぞれの感じ方をすれば。
 多感ゆえにもがく紀子に対して妹のユカのほうはもう少しさめている。そんなユカを自然に演じてみせるのが吉高だ。撮影は2年前だったからユカとは同い年だった。共感する部分も多かったろうと水を向けたら思案げに答えた。
多感ゆえにもがく紀子に対して妹のユカのほうはもう少しさめている。そんなユカを自然に演じてみせるのが吉高だ。撮影は2年前だったからユカとは同い年だった。共感する部分も多かったろうと水を向けたら思案げに答えた。
「私たちの目から観ても理解はできないんじゃないか、話が読めないのではないかと思います。そういうことも含めて観ていただいたうえでの率直な意見をお聞きしたいです」
ユカは単に主人公の妹という以上に、最後の最後に観客に問題を提起する役回りも担う。
「ユカは、たぶん上京してまのあたりにした出来事のひとつひとつによって何かが大きく変わったのでしょう。いろいろと考える子だし、想像力が豊かなんでしょう。最後の場面は、観るたびに違う感情がこみげます。観てくださる方によって違って映る場面になるでしょう。自分の感情と向かい合っていただけたらいいのでは」
しっかりとした受け答えという以上に冷静で客観的な分析には驚かされた。途中でノートを取り出してページを繰り出したので、何かと問うたら、前日映画を見直した際改めて感じたことを書き出したのだという。作品に対する熱心さには脱帽だ。

一方、女優としての自分について語る言葉はどこまでも謙虚だ。
「改めて観て、まず恥ずかしかったです。いろいろな部分が気になりました。よく指摘されるのですが、滑舌が悪いし、笑い方もぎこちない。ただ、そのときにしか感じられない感情というものを大切に演じました」
東京生まれ。高校1年生のとき原宿で買い物しているところをスカウトされた。“スカウトウーマン”だったので、なんとなく気を許して連絡先を教えてしまったのが始まりだった。
「お笑いをやりたいって言ったことはあります。だって、人が笑っているのを見ると幸せだから。笑いは温かい」。それも真剣な発言ではなかった。いわんや役者になりたかったわけではない。が、テレビに映る自分を観てみたいと思った。少女らしい好奇心か、そもそも事態を客観視する鳥の目の持ち主なのか。

「私はあきっぽいんですけど、演技の世界は終わりがなさそう。分からないことだらけだから、あきることがないんです。そもそも自分には何もわかっていない。手探りだから何にも納得できない。納得できない限りは、やめたくない。いまは何をどうしたいと具体的にいえないぐらい、ともかくいろいろなことを経験してみたいです」
そんなふうに考えるきっかけになったのも、この映画の撮影を通じてだったという。CM、テレビドラマ、映画…。いまは挑戦したいことが、たくさんある。

 「がっつきもしないけれど、ひっこみたくもない。競争の激しい世界だと分かっているけれど、『やばい、やばい』って急いでもしかたない。『別にいいや』っていったらおいていかれちゃう。一方で、自分がめぐりあうものはもう決まっているんじゃないかと思うこともあります。難しい。だけど、基本はマイペース!」
「がっつきもしないけれど、ひっこみたくもない。競争の激しい世界だと分かっているけれど、『やばい、やばい』って急いでもしかたない。『別にいいや』っていったらおいていかれちゃう。一方で、自分がめぐりあうものはもう決まっているんじゃないかと思うこともあります。難しい。だけど、基本はマイペース!」
焦らない。だけど、たゆまない。マイペース宣言は、しかし、確固たる自信の裏返しなのかもしれない。いや、まだ自信になりきっていない心に秘める何か、といったほうがいいか。ふしぎと意思の力を感じさせる目なのだ。深い池の底をのぞき込んだときのように吸い込まれそうな、不思議な輝きをもった目。
「小学校の卒業文集には『魔法使いになりたい』って書きました。他人とは違う力、他人がもっていないものをもちたい。空を飛んだり、壁をすりぬけたり、ほかの人には分からないものを人に伝えられたらすごいし」
女優という仕事は、そんな魔法の力に似たところがあるかもしれない。吉高由里子は女優という魔法使いへの大きな一歩を踏み出した。
産経Webは、産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。
すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)
(C)2006.The Sankei Shimbun All rights reserved.
 紀子の食卓 9月23日(土)東京・新宿のK'sシネマで公開 脚本・監督:園子温 出演: 吹石一恵 つぐみ 吉高由里子 光石 研 カルヴィヴァリ国際フィルムフェスティバル特別表彰&FICC賞受賞 プチョン国際ファンタスティック映画祭観客&主演女優賞 ●公式サイトはこちら
STORY 島原紀子は、17才の平凡な女子高生。妹ユカと両親の4人家族。紀子は田舎の生活や家族との関係に違和感を感じていた。ある日、"廃墟ドットコム"というサイトをみつけ、そこで知り合った女の子を頼りに東京へ家出を決行する。東京で<ミツコ>と名乗った紀子は、虚構の世界で生きることを決める。そんなある日、新宿駅のプラットホームから女子高生54人が集団自殺する。"廃墟ドットコム"にその秘密が隠されていることを知った妹ユカも東京へ消える―-。 PROFILE よしたか・ゆりこ 1988年7月22日 東京生まれ。「メゾン・ド・ヒミコ」DVD特典ショートフィルム「懲戒免職」、WOWOW「チルドレン」、ドラマ「時効警察」(テレ朝系)などに出演するほかCMなど。今回が映画デビュー。 ●公式サイトはこちら |

