 |
 |
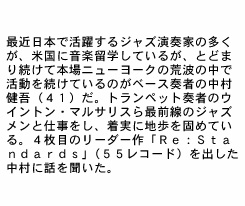 |
|
 |
|

見る前に飛ぶのが中村の生き方、のようだ。
最初にさわった楽器はクラシックギター。でも、本当はフォークギターで弾き語りをしたかった。自宅そばに「ギター教室」の看板をみつけて飛び込んだらクラシックギター教室だっただけ。
 結果的には指の使い方など後にエレキベースを弾く際に大いに役立ったが。
結果的には指の使い方など後にエレキベースを弾く際に大いに役立ったが。
高校生になってバンドを組んで、当時ブームだったアリスなどニューミュージックを演奏した。
ほかに演奏者がいなかったからベースを担当したら、ちょうどマイルス・デイビスのバンドなどでマーカス・ミラーが活躍し始めてベースがカッコいい時代になっていた。
大学時代はフュージョン系のバンドに入って本格的にベースを弾いた。ただ、ライブハウスなどに頻繁に出演したわけではなく、むしろ練習していることのほうが多かった。バイトで稼いだ小遣いはすべて練習スタジオのレンタル代に消えたが、それがストイックでカッコいいと思えた時代でもあった。
しかし、音楽で生計を立てたいと考え、大学卒業後は米国のバークリー音大に進むことを決めた。
同音大で音楽理論をみっちり学べば帰国後、音楽教室でのベース講師、あるいはスタジオミュージシャンになれるのではないか−−というもくろみもあったが、ともかく飛んでみないと分からないというわけだ。
卒業後の1年は、渡米費用を稼ぐためのアルバイトに費やした。それだけではなく結婚もした。
将来も見えず、渡米する身でふつう結婚はためらいそうなものだが、ここでも飛んでしまったというわけだ。ちなみに中村の父親は激怒したが、妻となる女性の両親は「理解があった」と、なんだか正反対のなりゆきだったそうだ。
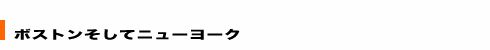
1988年、米ボストンのバークレー音大で学ぶため“中村夫妻”は渡米する。
バークレーでは最初エレキベースを学んだが、ベースの巨人、チャールズ・ミンガスの「ミンガス・アー・アム」という作品を聴き、そのうねりと躍動感に衝撃を受けてアコースティックベースに転向した。
 「単純といえばそうですね。猪突(ちょとつ)猛進なんですよ。すぐに周囲が見えなくなる」
「単純といえばそうですね。猪突(ちょとつ)猛進なんですよ。すぐに周囲が見えなくなる」
同じベースではもエレキとアコースティックとでは奏法がずいぶん違う。
「アコースティックベースの場合、左手は3本の指を使う。エレキは4本。器用な人は両方こなしますが、僕は、エレキは押し入れにしまってしまいました」
バークレーでの先輩、同期はみな帰国。そして日本で活躍した。たとえば先輩にピアノ奏者の大西順子がいる。ドラム奏者の大坂昌彦がいる。ともに1990年代に若手日本人ジャズブームを巻き起こした。
が、そんな仲間たちの活躍を横目に中村はニューヨークで腕試しをしようと決心する。日本の家族には「卒業したら、ちゃんと帰国する」といっていたのに、だ。
「興味のあるところには行ってみたい。経験して分かりたい。ニューヨークにいかずに帰国するのはいやだった。帰国するまでの道のりとしてニューヨークに行ってもいいのではないかと考えました」
仲間たちの帰国の背景には、ビザの問題もあった。学生ビザだから就学期間が終われば帰国せざるを得ない。中村は妻を学生にし、自分は同行者として滞在したのだった。

滞在の問題はクリアできても生活の問題は残った。ニューヨークに出た最初の3年は、アルバイトで糊口(ここう)をしのぎ、とりあえず路上演奏などを続けた。いまでこそ「いい練習期間だった」と振り返るが、苦しかった。
「自分はなにやっているんだろう。日本に帰ろうと思ったこともありました。日本の演奏家の招請で日本で仕事をしたとき、こんなに仕事があるのかと驚きもしたし」
それでもしがみついた。ライブハウスなどのジャムセッションに飛び込み始めたときは名刺を大量に作って配りまくった。
ジャムセッションで知り合ったドラム奏者に呼ばれて仕事に出かけたら、そのときのピアノ奏者がサイラス・チェスナットだった。90年代に破竹の勢いでシーンに登場した。共演したいと思っていたひとりだったので、忘れずに名刺を渡した。なくされたらたまらない、と2枚渡した。
そうしたら電話がかかってきた。こうしてサイラスのバンドで演奏することになった。97年。渡米から10年近くたっていた。
サイラスとの仕事を見て、ウイントンも声をかけてきた。現代を代表するトランペット奏者であり、さまざまな議論を呼びはするが、いまのジャズの理論的な主導者でもある。
「ウイントンは、スイングをすることを求める演奏家。スイングするって抽象的だからこそ、裏に深いものがある。たとえばビート感。たとえばうねり。音符として書けないものを求めるわけです。昔と違って情報量が抱負だから、日本人だからスイングできない−−という時代ではない。アフロアメリカン特有の強じんなバネはまねできないかもしれませんが、僕らは僕らのスイングをすればいいんです」
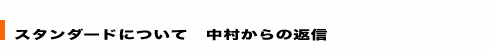
ニューヨークでの活動は次第に安定し始め、やがて日本を代表するピアノ奏者、小曽根真と出会い、彼の紹介などもありリーダー作CDを出す。
そして今回が4作目。表題どおりスタンダードソング集だ。スタンダード集にすることになったのも小曽根がきっかけだった。自作曲を中心に作品を作ってきたが、4作目の内容を検討している際、小曽根が4作目をスタンダード集にしていたことを知り、ピンとくるものがあった。
 表題の意味は「スタンダードについて」。冒頭の「Re:」は電子メールが普及したいまやすっかり見慣れた文字だ。
表題の意味は「スタンダードについて」。冒頭の「Re:」は電子メールが普及したいまやすっかり見慣れた文字だ。
「ニューヨークの街を歩いていて思いつきました。『Re:』はキャッチーだと思うし、同時に再びという意味にもつながる。僕というフィルターを通じて再びスタンダードを演奏するということにもなる」
いわばスタンダードについて中村からの返信ということだ。
まず10曲選んだ。バラードばかりが候補にあがり、バランスをとるためにアップテンポでも演奏できるものとして「イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー」と「オール・ザ・シングス・ユー・アー」を加えた。
「イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー」は冒頭を飾る。“切り込み隊長”にふさわしいアレンジをものにすることができたとき、肩の荷がおりた気分になったと振り返る。
ハリケーン「カトリーナ」の被災地であるニューオーリンズを仕事で訪問した際の鮮烈な記憶から「バーボン・ストリート」「懐かしのニューオーリンズ」の2曲も加えた。
「ミンガスは怒りを表現しましたが、あれは彼の活躍した時代が怒りの時代だったから。ジャズは世相に影響される音楽だと思うし、僕も今起きている世界のできごとを音楽で描きたい。僕の場合は平和のメッセージを託したい。魂を共有できるメッセージを出せたらいいですね」
ところで、最近のニューヨークのライブハウスは“ハプニング”が起きないのでおもしろくないという。若い世代が出てこない。ちょうど自分が次々に飛び込んでいたように、見る前に飛ぶような若い演奏家が少なくなったというのだ。
「僕がニューヨークでやってこれたのは、人のつながりが大きかった。僕には、あの人と共演したいという強い思いが常にあった。願わなければその人とつながることはできないし、願ったら飛び込んでいかなくてはだめですね」
もうしばらくニューヨークにいるつもりだ。もう少しだけ飛び込み続けたいから。
産経Webは、産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。
すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)
(C)2006.The Sankei Shimbun All rights reserved.
 Re:Standards 55 RECORDS FNCJ-5518 ¥2,500(税込)
演奏:中村健吾(B) マーカス・プリンタップ(TP) テッド・ナッシュ(AS,CL,AL-FL) ダン・ニマー(P) (1)(7)(11)小曽根真(P,OG) (1)〜(5)(8)〜(12)クラレンス・ペン(DS) 録音:2006.6 ●公式サイトはこちら ●中村健吾NYクインテット?Re: Standards ツアー 11/22(水) 大阪 Jazz on Top 11/24(金) 神戸 Satin Doll 11/25(土) 四日市 アソシエード第一 KAIEN'S ROOM 11/27(月) 京都 RAG 11/28(火) 横浜 Motion Blue 11/29(水) 名古屋 Doxy 11/30(木) 静岡 Koln 12/1(金) 東京 Body & Soul 12/2(土) 東京 Body & Soul 12/3(日) 館林 文右衛門ホール メンバー:中村健吾(b)マーカス・プリンタップ(tp)ウェス・“ウォームダディ”・アンダーソンン(as)海野雅威(p)高橋信之介(ds) (問) 55Records Tel. 03-5785-2357 |
