 |
 |
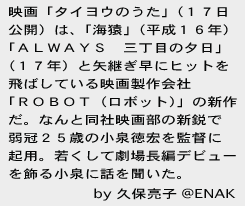 |
|
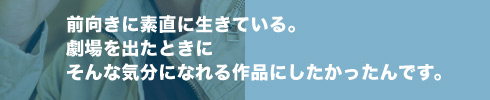 |
|


「短編なら責任はないというか人生に影響を与えることにはならないけれど、長編の場合は作品がいわば“名刺”になり、次の仕事にも影響します。失敗はできません。ましてやこれが1枚目の名刺ですから」
撮影は昨年9月12日から10月末の約1カ月半。初めての“舵取り”を「自分のテンションややる気が現場には浸透するので、“芝居をうつ”必要があるときもあります。しかし、そんな余裕もないことも少なくなかったから苦しみました」と振り返る。
紫外線を浴びることで皮膚に思い障害をもらたす病気、XP(色素性乾皮症)を背負った、歌の大好きな16歳の少女、雨音薫(YUI)と、サーフィンに夢中な男子高校生、藤代孝治(塚本高史)とのさわやかな恋を描く。
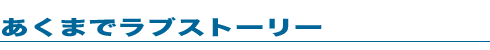
「脚本を読んだのは昨年の5月で、すでにその2、3年前から難病、純愛、韓流モノがはやっていました。その流れは(「タイヨウのうた」が公開となる)1年後には終わってるかもしれないと考えましたが、終わっていようがいまいが新しい描き方があると思いました。病気であることに同情を買うのではなく、前向きに素直に生きている。劇場を出たときにもそんな気分になれる作品にしたかったんです」

 うたうことに生きることを重ねる薫を演じるのは、これが女優デビューとなるシンガーソングライター、YUI。長編デビューの監督と新人女優のタッグだが、不安はなかった。
うたうことに生きることを重ねる薫を演じるのは、これが女優デビューとなるシンガーソングライター、YUI。長編デビューの監督と新人女優のタッグだが、不安はなかった。「この作品で大切なのは、いい歌をきちんとうたえること。むしろ、ここがよくないと成立しない。よしんば演技が多少ぎこちないとしても、薫は社会と接点がないのだからそういうこともあるというふうにも考えていました」
作品の舞台ともいえる薫の部屋。そこには彼女らしい世界が漂っている。鎌倉の一軒家の2階。朝日がうっすらと差し込むころ、サーフィンにやって来る孝治の姿を窓際から探す。孝治を海へ“送り出す”と、薫は紫外線を遮断する青みがかったフィルムをスルスルと下ろし、押し入れを改造したベッドに潜り込む。
「実際の患者さんの家庭では、透明のフィルムを窓ガラスに張ることがほとんどのようですが、映像としては分かりづらいのでそうしました」とフィルムについては説明する。
ただ雨音家の自家用車に取り付けたフィルムは、その奥に座る薫の表情をカメラがとらえられるように透明なものを使った。フィルムに気づかない人もいるかもしれないが、風にはためき続ける効果音を聞き逃さないでほしい。繊細なテーマに配慮しながらの映画表現だ。
「病気を中心に描くのではなく、あくまでラブストーリーとして仕上げた。路線としては自分の思ったとおりだったと思う。楽しい時間があってこそ、悲しい時間が生きてくる」

映画に目覚めたのは高校時代だったという。国語の教師から、夏目漱石の代表作「こころ」についてレポートにするか、映画にするかという課題を出された。迷わず映画を選んだ。

「明治時代の話なのに、Gショック(腕時計)つけたまま出てるんですよ。せっかく現代的なものが背景に映らないよう撮ったのに、Gショックつけたままなんだもん」。思春期を語る口調は朗らかだ。
このとき学び、その後のこだわりとなったのが音楽だという。
「どんな音楽をのせるかで映像が違ってくる。(「こころ」の課題で)映像と音楽との融合。そのエネルギーに衝撃をうけました」
 実際、この「タイヨウのうた」でも一番好きな場面は、薫が横浜で路上でうたっている場面から孝治のバイクにまたがるまでの流れなのだという。
実際、この「タイヨウのうた」でも一番好きな場面は、薫が横浜で路上でうたっている場面から孝治のバイクにまたがるまでの流れなのだという。
「劇中の薫の歌声からバイオリンが奏でるBGMに切り替わって走り出していく。音楽がふたつの場面をひとつの流れにしているんです」
「笑って、笑って、最後に感動する作品」。これから作りたい作品の夢を口にする。
「人間のえげつない部分を描くようなダークなものも撮ってみたい。でも、25歳なので、まだ早いかな」
漱石の「こころ」は人間の悲しみと心のあやを「私」の視線で浮き彫りにした文学だ。いくつかの“名刺”ができあがったとき、その“原点”で出会った作品のテーマ、人間のすごみを、小泉流で再び描くかもしれない。
タイヨウのうた
出演:YUI、塚本高史、麻木久仁子、岸谷五朗原作/脚本:坂東賢治
音楽:YUI/椎名KAY太
●Profile
こいずみ・のりひろ 昭和55(1980)年、東京生まれ。水戸短編映像祭をはじめ、国内外の映画祭で入賞。篠崎誠監督が発案者となった「刑事まつり」に「行列のできる刑事」を出品。高い評価を得る。現在、ROBOT映画部に所属。
***
「タイヨウのうた」撮影後、自身への“ご褒美”は 携帯音楽プレーヤー「iPod nano」と、普通自動二輪免許の取得。免許のきっかけは、「たまたま街ですれ違ったバイク、『スズキ、ST250 Sカスタマイズ』に心を討ちぬかれて」。
携帯音楽プレーヤー「iPod nano」と、普通自動二輪免許の取得。免許のきっかけは、「たまたま街ですれ違ったバイク、『スズキ、ST250 Sカスタマイズ』に心を討ちぬかれて」。
***
ENAKが観た「タイヨウのうた」はこちら

