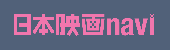ユペールは“炎”になった
フランス映画「ジョルジュ・バタイユ ママン」
7月18日(火) 東京朝刊 by 黒沢綾子
フランスの思想家、ジョルジュ・バタイユの小説『聖なる神』をもとに、舞台を現代に移して映画化した「ジョルジュ・バタイユ ママン」(仏、2004年)が、東京で公開されている。快楽と死という禁制を侵すことで人間はエロスを味わい、冒涜(ぼうとく)によって神に近づく−。鬼才の根本的思想が、母と子のスキャンダラスな関係の中であらわにされてゆく。
自堕落な父親から解放され、敬愛する母親に会いにやってきた17歳の少年。ところが、青い海ときらめく太陽の下、ママンは本性をあらわにし、息子をエロスの狂宴へと導く。美しくも残酷な母親を「“炎”にたとえて演じた」と女優、イザベル・ユペールは語る。
「彼女は退廃的な生活と絶望、あるいは生きたいという欲望と死への欲望の中を揺れ動く。他人が触れればやけどをする。そして自ら燃え尽き果て、最後には消えてしまう」
バタイユ作品の映画化にあたっては、その意味について懐疑的見方もあったという。「監督のクリストフ・オノレは作家でもあるので、この危険な賭けに出たのでしょう。バタイユは独特の世界を持つ別格の存在。彼自身カトリックであり、高い精神性と卑俗なものを混ぜ合わせ、デリケートで難しい空間を描こうとした。文学にはできて、映画にできないこともある。言葉でにおわせることができても、映像では表現できない部分も」とユペール。
「映画はすべて描けるものではない」というのは、女優としての実感だ。今回の「ママン」もしかり、特異な性的嗜好(しこう)に悩む主人公を演じた「ピアニスト」(2001年)など、ユペールは難しい役柄に挑んできた。「(世間一般の)道徳的に見れば受け入れられないが、それなりに存在の正当性がある作品もある。その場合、見せるシーンと見せられないシーンをきちっと選ぶ倫理観こそ、私の出演基準。その差異は非常に小さく、ギリギリの線なのですが、一線を越えないからこそ、俳優はその世界に飛び込み、冒険できるのです」
ママン役のオファーに当初、ユペールは躊躇(ちゅうちょ)したという。が、結論は「ウィ」。それは彼女自身が、この作品を世に問う意義を見いだしたからに他ならない。
 |
| 映画「ジョルジュ・バタイユママン」から((C)GeminiFilms) |
自堕落な父親から解放され、敬愛する母親に会いにやってきた17歳の少年。ところが、青い海ときらめく太陽の下、ママンは本性をあらわにし、息子をエロスの狂宴へと導く。美しくも残酷な母親を「“炎”にたとえて演じた」と女優、イザベル・ユペールは語る。
「彼女は退廃的な生活と絶望、あるいは生きたいという欲望と死への欲望の中を揺れ動く。他人が触れればやけどをする。そして自ら燃え尽き果て、最後には消えてしまう」
 |
| 欲望に身を焦がす母親を「“炎”にたとえて演じた」と語るイザベル・ユペール |
バタイユ作品の映画化にあたっては、その意味について懐疑的見方もあったという。「監督のクリストフ・オノレは作家でもあるので、この危険な賭けに出たのでしょう。バタイユは独特の世界を持つ別格の存在。彼自身カトリックであり、高い精神性と卑俗なものを混ぜ合わせ、デリケートで難しい空間を描こうとした。文学にはできて、映画にできないこともある。言葉でにおわせることができても、映像では表現できない部分も」とユペール。
「映画はすべて描けるものではない」というのは、女優としての実感だ。今回の「ママン」もしかり、特異な性的嗜好(しこう)に悩む主人公を演じた「ピアニスト」(2001年)など、ユペールは難しい役柄に挑んできた。「(世間一般の)道徳的に見れば受け入れられないが、それなりに存在の正当性がある作品もある。その場合、見せるシーンと見せられないシーンをきちっと選ぶ倫理観こそ、私の出演基準。その差異は非常に小さく、ギリギリの線なのですが、一線を越えないからこそ、俳優はその世界に飛び込み、冒険できるのです」
ママン役のオファーに当初、ユペールは躊躇(ちゅうちょ)したという。が、結論は「ウィ」。それは彼女自身が、この作品を世に問う意義を見いだしたからに他ならない。