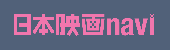ENAKが観た映画「ハイジ」
アニメ世代も裏切らない
7月6日(木) 久保亮子@ENAK
映画「ハイジ」を観てきた、と同世代の友人たちに話したら、懐かしさのあまりつい“ハイジ談議”に花が咲いてしまう。
ブラウン管から主題歌「教えておじいさん」の出だしのアルプホルンが聞こえてくるだけでワクワクした。伸びやかな歌声を背景に、ハイジは空から垂れ下がるブランコをこぎ、ふわりと雲の上に飛びのると、アルプスの山並みを見下ろしながら無邪気に笑う。おじいさんの作るチーズフォンデュ、干し草のベッド、子ヤギのユキちゃん−。私も「雲に乗れる」と思っていたひとりだ。
思い入れがある作品だけに、この実写版には裏切られはしないかと構えていたが、杞憂(きゆう)に終わった。それどころか涙がこぼれた。深みのある人物描写もさることながら、大人だからこそ理解のできる悲しみが隠されているからだ。
原作は1880年に発表されたスイス人女性作家、ヨハンナ・シュピリの同名小説。ヨハンナは、ハイジにヨーロッパ寓話特有の悲劇性、恵まれない境遇を負わせてはいるが、一方で世界中のファンが魅了されることになる明るさを彼女に与えた。
ポール・マーカス監督も製作にあたって「ハイジには、人々の生活に光をもたらすような資質をもたせた」と語る。
ハイジは、アルムの孫娘。
「おじいさん、お父さんはどんな人だったの?」と尋ねるハイジに、アルムはハイジをしばらく見つめてから優しく答える。
「お前にそっくりだよ」
表情が心を描きだす。これが実写版ならではの魅力だ。銀幕のなかでハイジを見つめるアルムのまなざしは私の涙をしぼった。
もちろん、ハイジのおてんばぶりは実写版でも健在。フランクフルトでは、ペーターのおばあさんに食べさせてあげる白パンをクローゼットの中にため込んでカビだらけにした。屋敷にもらい手のない子猫を連れ帰り、動物嫌いの執事、ロッテンマイヤー夫人を気絶させ、お説教の最中には居眠りもする。
テレビアニメでも観たそんな場面に懐かしさがこみ上げたり、ハイジの利発さに目を細めたり。
フランクフルトを去り、やがてクララがアルプスに遊びに来る。遊び相手を奪われ、ふてくされるペーター。ハイジはクララに小声でささやく。
「私たちにヤキモチをやいているのよ」
かつてブラウン管越しの友だちだったハイジに、今では愛しさを感じる。あのころの私たちは、すっかり大人になったのだ。

ブラウン管から主題歌「教えておじいさん」の出だしのアルプホルンが聞こえてくるだけでワクワクした。伸びやかな歌声を背景に、ハイジは空から垂れ下がるブランコをこぎ、ふわりと雲の上に飛びのると、アルプスの山並みを見下ろしながら無邪気に笑う。おじいさんの作るチーズフォンデュ、干し草のベッド、子ヤギのユキちゃん−。私も「雲に乗れる」と思っていたひとりだ。
思い入れがある作品だけに、この実写版には裏切られはしないかと構えていたが、杞憂(きゆう)に終わった。それどころか涙がこぼれた。深みのある人物描写もさることながら、大人だからこそ理解のできる悲しみが隠されているからだ。

原作は1880年に発表されたスイス人女性作家、ヨハンナ・シュピリの同名小説。ヨハンナは、ハイジにヨーロッパ寓話特有の悲劇性、恵まれない境遇を負わせてはいるが、一方で世界中のファンが魅了されることになる明るさを彼女に与えた。
ポール・マーカス監督も製作にあたって「ハイジには、人々の生活に光をもたらすような資質をもたせた」と語る。

ハイジは、アルムの孫娘。
「おじいさん、お父さんはどんな人だったの?」と尋ねるハイジに、アルムはハイジをしばらく見つめてから優しく答える。
「お前にそっくりだよ」

表情が心を描きだす。これが実写版ならではの魅力だ。銀幕のなかでハイジを見つめるアルムのまなざしは私の涙をしぼった。
もちろん、ハイジのおてんばぶりは実写版でも健在。フランクフルトでは、ペーターのおばあさんに食べさせてあげる白パンをクローゼットの中にため込んでカビだらけにした。屋敷にもらい手のない子猫を連れ帰り、動物嫌いの執事、ロッテンマイヤー夫人を気絶させ、お説教の最中には居眠りもする。
テレビアニメでも観たそんな場面に懐かしさがこみ上げたり、ハイジの利発さに目を細めたり。
フランクフルトを去り、やがてクララがアルプスに遊びに来る。遊び相手を奪われ、ふてくされるペーター。ハイジはクララに小声でささやく。
「私たちにヤキモチをやいているのよ」
かつてブラウン管越しの友だちだったハイジに、今では愛しさを感じる。あのころの私たちは、すっかり大人になったのだ。